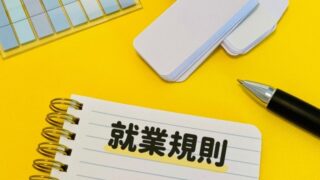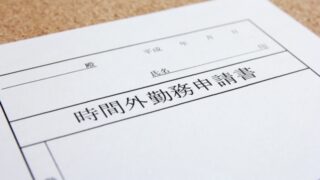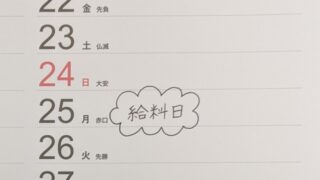社会保険労務士
社会保険労務士 社労士独学勉強法【まとめ】~夢の社会保険労務士合格へ~
社会保険労務士試験は難関資格ですが、独学合格は十分可能です。これから勉強のために人生の貴重な時間を費やしていくわけなので、スタート段階でしっかり検討してから取り組むべきです。私の体験記を読んで、自分も独学でできそうと考えたら挑戦してみてください。ちょっと自分には難しいと思ったら予備校を利用してみてください。
どちらにせよ、難関資格の合格は自分次第。正しい努力をして合格への最短距離を進んでいく必要があります。私の完全独学での合格体験は、そのための重要な情報になると信じております。